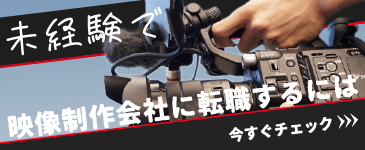インタビュー動画を撮影する時に重要になるのが音声の収録です。
動画撮影で音声収録は
・ガンマイク
・ワイヤレスマイク
・ICレコーダー
・ピンマイク
主に以上の4つの方法がありますが、ここではインタビュー動画撮影初心者さん向けにインタビューをクリアな音質で収録するためのポイントとオススメ機材を紹介します。

2024年 2月 監修者:ビデオ制作ディレクター / MDM合同会社 代表 水田吉紀
2012年 営業職から映像製作会社に転職し、映像カメラマンの業務に携わる。
2020年 MDM合同会社を設立。主に関西エリアでビデオ撮影・動画編集の仕事を請け負っている。
![h2]()
インタビュー動画では映像も大切ですが、それ以上に音声の品質が重要になります。

極端な話、音質が良ければ画質が悪くても見てもらえます。両方悪いと×
クリアな音声を収録するためにも、その方法と注意しなければならないポイントをおさえておきましょう。
こちらもオススメ:失敗しないインタビュー動画の作り方|Vook

インタビュー動画で欠かせないのがマイクです。
相手の声をしっかり収録するためにも、複数のマイクがあった方が良いのですが、ここではまずガンマイク1本で収録することを想定して解説します。
ガンマイクと併用してピンマイクを使うのが最善ですが、ピンマイクは品質の良いものを揃えようとすると高価になります。
また装着に慣れていないと時間がかかったり、衣装のタイプによっては使いにくい場合などがあります。
初めのうちはガンマイクの方があらゆる状況に柔軟に対応できて便利でしょう。
また、ガンマイクは感度が非常に高いため、音声をしっかり録ることが可能です。
意識的に大きな声を出さなくても音声を拾ってくれるため、インタビューを受ける人はより自然体で話をできます。
高品質なガンマイク(と言っても4万円以内で手に入る)を使えば、マイクとの距離が極端に離れない限り、ピンマイクよりも音質が自然な仕上がりになります。
ピンマイクとは違い、マイクの位置も自由に調整できるので理想的なインタビューの撮影環境を作り出せます。

ガンマイクを使う場合は、必ずショックマウントとウィンドスクリーンを用意しておきましょう。

まずショックマウントとはガンマイク本体とカメラの接続部分に装着するアイテムで、マイクに振動などが伝わるのを防いでくれます。
たとえば三脚を使わずにハンディで撮影する場合、ショックマウントを装着することでマイクが揺れてノイズを拾ってしまうのを軽減します。
また一眼カメラで収録する場合、ショックマウントがあることでカメラとマイクの距離が少し離れ、レンズの駆動音(AF駆動音)を収録してしまうことも防げます。
風が強いと風の音もマイクが拾ってしまいますが、このような環境音を防いでくれるのがウィンドスクリーンやウィンドジャマーと呼ばれるマイクアクセサリーです。

屋内なら風も吹かないので不要と考えてしまいがちですが、室内ではエアコンを使うことがありますし、風だけではなく雑音防止にもつながります。
必要な音声だけを拾うことが可能になるので、ガンマイクを使ったインタビュー動画ではウィンドスクリーンが欠かせません。

安価なアイテムなのでマイクのサイズに合わせて用意しましょう
雑音は動画編集のソフトウェアで除去することも出来なくはないですが、編集作業の負担が大きくなりますし、ノイズ除去は面倒な作業です。
それならば最初からショックマウントとウィンドスクリーンを装着し、雑音が入らないようにしましょう。

ガンマイクの配置は主に2パターン考えられます。
1つはカメラのマイクシューに設置する方法、そしてもう1つがインタビューの対象者のすぐ近くに配置する方法です。


インタビューイーに近い方がしっかり音声を拾えますが、感度が高いガンマイクであれば多少距離があっても問題ありません。
カメラ目線で話すインタビュー動画では、カメラのマイクシューに設置するのが良いでしょう。
マイクをインタビュー対象者に近づける場合はマイクスタンドや三脚を使ったり、人の手でマイクをなるべく固定することも重要です。
まずは配置を決めてしまい、その配置にしっかり固定できるよう工夫しましょう。
クリアな音声のインタビュー動画を撮影するなら、ガンマイクが役立ちます。


インタビュー動画に欠かせないガンマイクとして、ゼンハイザーのMKE600をオススメします。
非常に強い指向性が特徴のガンマイクで、横や後ろからのノイズはしっかりと減少しつつ、正面方向からの音を確実に拾ってくれます。
プロのクリエイター向けに作られているだけあって剛性もあり、性能も非常に優れています。
この製品の上位モデルであるゼンハイザー MKH416は映像業界の定番マイクとして広く使用されています。
しかし、10万円を超える価格なので、低予算の撮影仕事ではちょっと手が出しにくいでしょう。
一人で撮影して編集するインタビュー動画ならMKH416の下位モデルであるMKE600でも十分です。
ガンマイクは感度が良いのがメリットですが、指向性が弱いと音を拾いすぎてしまう可能性もあります。
MKE600は指向性が極端なぐらい強く、狙った被写体の音声をクリアに収録できます。
またMKE600にはショックマウントが付属されていて、余計な振動によるノイズなどを抑えてくれます。
さらにローカットフィルターという機能を利用することで、風のノイズをはじめさまざまなノイズも抑えてくれます。
余計なノイズをカットしつつ、明瞭で聞き取りやすい音声を収録可能です。
また、ピンジャックでデジタル一眼レフカメラのマイク端子に接続可能という点も便利です。
残念ながら接続ケーブルは別売りですが、デジタル一眼レフカメラでのインタビュー動画撮影にも対応できてしまいます。
クリアな音声のインタビュー動画を撮影するなら、ゼンハイザーのMKE600が役立ちます。
映像クリエイターみんな大好きサウンドハウスが最安値です。
![h2]()
インタビュー動画の撮影で、音声をワイヤレスマイクで録る場合の使用手順を確認しておきましょう。


まずはマイク本体と受信アンテナがしっかり送受信できるかを確認しましょう。
ワイヤレスマイクは余計なケーブルがないため非常に便利ですが、信号を送受信できなければ音声を録れません。
一般的なワイヤレスマイクの場合、マイクから送られる信号を受信機のアンテナが拾って音声を収録しています。
そのため信号が受信アンテナに送られるまでの間に、なんらかの障害物があると正しく送受信できなくなる可能性があります。
障害物というのは物もそうですが、人も当てはまります。
たとえばステージの上に立ち、前にいる観衆に向けて話をするような場合、観衆の後ろに受信アンテナを配置してしまうと、人が障害物になったりするのです。
ワイヤレスマイクを使う時は、受信アンテナの位置に気を付けましょう。
具体的には受信アンテナはなるべく高いところに設置し、信号の通る道を作ってあげます。

ノイズが入ると機器の不調を真っ先に疑ってしまいますが、設置環境も重要です
高い場所なら障害物も無いので、スムーズな送受信が可能になり、クリアな音声を収録できます。
壁に設置するなどして、なるべく周囲に障害物が無い状態を作り出してあげましょう。

受信アンテナを正しく設置しないと、音声が録れていなかったり、ノイズが発生したりトラブルの原因になります。
音声収録に失敗して撮り直しとなれば時間も手間もかかりますので、こうしたトラブルは確実に予防しなければなりません。
マイクと受信機の配置間隔は、マイクの波長の4分の1の長さが基準になると言われています。
優れたダイバーシティ性能を確保するために、アンテナを、少なくとも波長の4分の1の長さ(800 MHzの場合は約10cm)の間隔に配置します。受信機のアンテナはワイド「V」設定で角度を付けて離して設置します。こうすることで、受信機を移動させたり、異なる角度に持ち替える場合に、より良いピックアップ性能を提供します。
ワイヤレス使用時に注意すべき5つの間違い|SHURE
これを基準として受信アンテナを配置しておけば、余計なトラブルの回避につながります。
インタビュー動画の場合、マイクと受信機の距離が極端に離れることはないと思いますが、マイクと受信機の距離に注意すればノイズ対策にもなります。


ワイヤレスマイクで重要な設定の1つが周波数の設定です。
周波数の設定が正しくできていないと、やはり音声の収録が難しくなります。
そこでまず気を付けたいのが周波数の混信です。
撮影会場には様々な周波数の電波を使っている可能性があります。もうすでに使われている周波数は使えません。
事前にワイヤレスマイクを使用する会場の周波数をチェックしておき、それ以外の周波数を使うようにしましょう。

テレビや他のワイヤレスマイクでも混信するので注意が必要です
さらに周波数は相互互換性を確保しなければなりませんが、このあたりの設定は非常に複雑で大変な作業です。
ワイヤレスマイクにはあらかじめ用意されている周波数があり、それらを使うのが手軽な方法となります。
この方法なら単純に用意されている周波数を使うだけでよく、余計な手間がかかりません。
インタビュー動画の撮影や、ワイヤレスマイクを使うのが初めてという方でも十分に対応できるでしょう。
またSONYのワイヤレスマイクUWP-D11については、送信機・受信機が自動で空いている周波数を選んでくれる機能もあります。

ワイヤレスマイクは電池を電源にしています。
対応電池なら何でも良いと考えてしまいがちですが、実は電池によってはノイズの原因になったりします。
というのも、電池の電圧が低くなってしまうと、ワイヤレスマイクの性能も落ち、ノイズが発生したり音声が不明瞭になるなどのトラブルが起きる可能性があります。
一般的なワイヤレスマイクは、使い捨てタイプのアルカリ乾電池を使用することを推奨しています。
これは電圧が安定するという特徴を持っているからで、他のタイプの乾電池よりもワイヤレスマイクに向いています。
コスト削減の観点から充電式の乾電池を使いたくなると思いますが、使い捨てタイプよりも電圧が低いので注意しましょう。
もちろん音質に問題ないなら充電式でも良いのですが、まずは使い捨てと充電式を両方使ってみて比較してみるのが良いかもしれません。
もし充電式電池でノイズが出るようであれば、使い捨てタイプのアルカリ乾電池を使いましょう。
また、ワイヤレスマイクの使用が終わったら必ず電池は外しておきます。
電池を入れたままだと液漏れの可能性がありますし、電池の残量がわからなくなります。

撮影現場で電池を外すクセを付けておきましょう
充電式ならすぐに外して充電し、使い捨てタイプならできれば次回の撮影では新品を使いたいところです。

ワイヤレスマイクを正しく利用するにはゲイン調整が必須です。
設定を間違うとノイズが発生したり、音が小さすぎたりします。
適切な調整は細かい部分まで含めると、その場でチェックしながら微調整するしかありません。
マイクテストを行いながら、丁度よい設定を見つけましょう。
基本的にはオーバーロードやピークインジケータのランプが時折点滅するくらいが丁度よいとされています。
これを基準として考えながら、後は現場で微調整すれば最適な設定が可能になるでしょう。
以上のような点に気をつけておけば、失敗せずにワイヤレスマイクを使用できます。
![h2]()

インタビュー動画に使いやすいオススメのワイヤレスマイクはSONYのUWP-D11で、コンパンダ方式が採用されているワイヤレスマイクです。
コンパンダ方式というのは、送信機側で音を圧縮し、受信機側で伸張するという仕組みのことで、音質を左右する重要な要素となります。
UWP-D11はデジタル処理にも対応していて、比較的安価なマイクでありながら一定の音質を確保してくれます。

小予算の動画制作には欠かせない機材ですよ
本格的なマイクと比べればやはり音質も負けてしまいますが、使いやすく便利なマイクと言えるでしょう。
インタビュー動画の撮影には充分な性能です。
またもう一つの利点として、UWP-D11は旧モデルのワイヤレスマイクセット UWP-V1とも交信できます。
ソニー以外にもTASCAMやゼンハイザーなどいろんなメーカーのワイヤレスマイクセットが販売されていますが、SONYは旧モデルとの互換性も良いのが人気の秘密です。
映像業界ではUWP-D11の音質は中ぐらいと評価されていますが、私個人的には混信やノイズが起こることも少なく安心して使えています。
小予算のインタビュー動画ならUWP-D11で十分高品質な音声収録が出来ます。
ワイヤレスマイクで音質の良い音声を録れば、インタビュー動画のクオリティはさらに上がります。
※UWP-D11が販売終了となり、後継機のUWP-D21が発売されています。
![h2]()
インタビュー動画を、ICレコーダーとピンマイクで収録する時のポイントも解説しておきます。


ICレコーダーは、内部にフラッシュメモリなどの記録用メディアが入っていて、音声を収録する目的で使われます。
録音のための装置と考えても良いでしょう。
基本的には人の声を録音するために作られているので、インタビュー動画の音声収録にも適しています。
動画はカメラで撮り、音声はICレコーダーで録音するといった感じになります。
動画編集時に音を合わせる必要があるので面倒ですが、確実にクリアな音声を撮るための手段の一つです。
ワイヤレスマイクやガンマイクの予備・保険としてICレコーダーで収録する場合もあります。
インタビュー収録時の使い方はシンプルで、ICレコーダーに搭載のマイク部分を相手に向けて録音を開始します。

指向性はないので、被写体のすぐそばに置きます
ガンマイクなどと違い、それほど音をしっかり拾ってくれるわけではないので、相手に向けるというのが重要になります。
マイク部分にはショックマウントなども付けられないため、機種によってはノイズ対策が難しい可能性もあります。
ノイズキャンセル機能が付いたものや、手動で入力感度を調整できるものなどを選ぶとノイズ対策もしやすいでしょう。

また、近年のICレコーダーには全方位で収録して、編集時にマイクの向きを選択できるICレコーダーがあるそうです。
あらゆる方向の音を撮って後でピックアップするなんて使い方ができるので、次世代のICレコーダーといったところでしょう。
業界の最先端を担うクリエイターさんが紹介しているので、今後普及が予想されますね。


ピンマイクは小型のマイクでインタビュー対象者の衣装に取り付け、音声をしっかり拾ってくれるのが利点になるでしょう。
ICレコーダーとピンマイクを併用して使うのが定番です。
通常は胸元あたりに、衣装の上から付けることになります。
感度も良く、高音質な音声を収録できますがノイズには注意が必要です。
ピンマイクでよくある失敗が衣ズレです。
話している人がピンマイクを直接触ってしまったり、会話中の身振り手振りで衣服がピンマイクに当たってノイズを収録してしまう現象です。
特にマイクを付けて話すことに慣れていない人によく見られます。
収録した音声はかなり大きな雑音になってしまうので、インタビュー中はマイクに触れないよう注意してもらいましょう。
またピンマイク用のクリップは汎用の製品がAmazonで数百円程度でも売っていますが、仕事で使うならSONYのクリップがオススメです。

このクリップは単品で購入すると3,000円以上で結構高価に感じると思いますが、実は衣ズレを防ぐ機能が満載です。
まず上の写真を見てもらえばわかると思います。ケーブルを固定する溝が用意されています。


まずマイクのケーブルを下から回すようにして固定溝に引っ掛けながらクリップで挟むようにして使います。
インタビューイーに取り付ける前にここまで準備しておくとよいでしょう。


今回の例では分かりやすくするためにシャツに取り付けていますが、実際に取り付ける場合はジャケットやスーツの下襟(ラペル)に取り付けることが多くなります。
ネクタイに取り付ける人もいますが、衣擦れを起こしやすいので私はネクタイにつけてもらうことはありません。位置は理想的なのですが..
スーツの下襟の裏側でケーブルも一緒に挟むようにして取り付ければ、ピンマイクも安定するので衣ズレも起こりにくくなります。
取り付ける場所は口とマイクの距離がインタビュー中に変化しない場所に取り付けることができれば問題ありません。

値段がちょっと高いアイテムは細やかな機能が備わっているんですねえ
SONYのクリップを正しく使うことで高品質な音声収録が実現できます。
汎用品でも取り付け方を工夫することでノイズを最小限に減らすことができますよ。
![h2]()
この記事をまとめると
・初心者さんはまずガンマイクが低コストでオススメ。ノイズを軽減するアイテムを活用しよう
・ワイヤレスマイクは周波数の設定に注意。電池はアルカリがベター。
・ICレコーダーはVR収録が最近のトレンド
・ピンマイクは取り付け方に注意が必要
こんな感じです!
インタビュー動画の音声収録は機材を揃えてポイントを押さえれば品質がかなり改善するはずです。
簡単なインタビュー動画ならプロに依頼しなくても問題なく制作できるのでぜひ挑戦してみてください。
そして、撮影後に音声ノイズを収録してしまったとしても、動画編集ソフトでノイズをキレイに消す方法もあるので困ったときは以下のページをご覧ください。