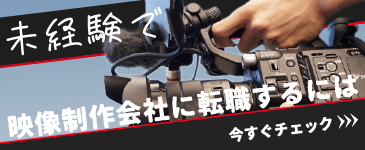ここではライブ配信に使うとオススメのオーディオインターフェースを紹介します。
トークライブ用途と楽器演奏・音楽ライブ用途で必要となる機能が少し違うので、目的別に合計9台紹介します。
オーディオインターフェースを使ったことがない方向けに、オーディオインターフェースの選び方のコツについても解説するのでじっくり読んでみてください。

2024年 2月 監修者:ビデオ制作ディレクター / MDM合同会社 代表 水田吉紀
2012年 営業職から映像製作会社に転職し、映像カメラマンの業務に携わる。
2020年 MDM合同会社を設立。ライブ配信業務を中心にビデオ撮影・動画編集の仕事を請け負っている。
オーディオインターフェイスとは?

オーディオインターフェイスはDTM(音楽の作成・編集)や、ライブ配信に欠かせないアイテムです。
その役割は、アナログ信号をデジタル信号に変換するものになります。
アナログ信号とは音声や楽器の音のことで、これをデジタル信号に変換してパソコンへ入力する、または逆にデジタル信号からアナログ信号への変換がオーディオインターフェイスの役割だと考えてください。

上の図はオーディオインターフェースを使ってライブ配信を行う時の一般的な接続を表しています。
パソコンにはオーディオ入力端子やUSB端子が備わっているので
「マイクをつなげれば音を取り込めるのでオーディオインターフェースは必要ないのでは?」
と考えるかもしれません。
これはこれで決して間違っていません。その通りです。
パソコンにはマザーボードに「サウンドデバイス」という機能が備わっており、ここ数年で飛躍的に性能が向上しています。
オーディオインターフェースなしでもかなりキレイな音でアナログ⇔デジタル変換できるようになってきています。
ただし、オーディオインターフェースも素晴らしい新製品が登場しており、パソコン内蔵のサウンドデバイスとは比べものにならないほど高品質な音声入力ができるものもあります。
また、パソコン内蔵のサウンドデバイスでは音を取り込むことはできても、音質が劣化してしまうなどのデメリットもあるのです。

そのためクリエイティブな場面や、音質にこだわったライブ配信をしたいという場合は、音質劣化が少ないオーディオインターフェイスが必要となります。
またオーディオインターフェイスを使うことで、パソコン本体の負担を軽減することも可能です。
ライブ配信は「OBS Studio」や「Streamlabs OBS」といったライブ配信専用のソフトを利用します。
ライブ配信ソフトは配信と同時に画面を録画するなど多機能で、テロップや画像を挿入するなど高品質なライブ配信が実現できます。
このような場合、パソコンのサウンドデバイスの負荷を分散するために、オーディオインターフェイスを別に用意することで安定感のあるライブ配信ができるようになります。
基本的にオーディオインターフェイスが必要となるような場面は2つです。
1つはDTMなどで音楽を作成するケースになります。
楽器やマイクとパソコンの間にオーディオインターフェイスを通すことにより、生の音を劣化させることなく録音・取り込みができるのが特徴です。
声や楽器の音そのものが聞き分けやすくもなるのも強みでしょう。
さらにオーディオインターフェイスを使うことで、遅延させないという強みも出てくるのです。
パソコンのサウンドデバイスで発生しやすいレイテンシ(遅延)を防いでモニタリングできるため音楽のライブ配信をするのなら必須とも考えられています。
もう1つはライブ配信を行う際です。
簡易的な配信で良いのなら、オーディオインターフェイスにこだわる必要はありません。
ですが音質にこだわった配信をしたいのなら、音質劣化が少なくなるというのは大きなメリットです。
ライブ配信にオーディオインターフェイスって必要?

ライブ配信にオーディオインターフェイスを使う意味を、もう少し掘り下げて見ていきましょう。
先述したようにオーディオインターフェイスがなくても、ライブ配信そのものを行うことは可能です。
ですがどうしても音質という点で言えば、機材があるのとないのとでは大きな違いが出てしまいます。
そのため音質にこだわったライブ配信をするのなら、オーディオインターフェイスは必須だと言えるでしょう。
またオーディオインターフェイスには、別の機能もあります。
それは様々なエフェクトがかけられるという点です。

例えばライブ配信者に人気のオーディオインターフェース YAMAHA AG03には音声入力時にあらかじめ設定しておいたエフェクトをボタン一つでかけられるという機能が備わっています。
当然エフェクター機能を搭載している機材に限られますが、声にエフェクトをかけることで映像表現の幅を広げられます。
エフェクト自体はライブ配信ソフトを使うことでも実現できますが、レイテンシの問題が発生します。
音の遅延があると実際に話している声と、エフェクトにズレが出てしまうのです。
これではせっかくのエフェクトも意味がありません。
ですがオーディオインターフェイスを使えば、遅延による音ズレを心配しなくて良くなるのです。
もう1つライブ配信にオーディオインターフェイスを使うメリットとしては、コンプレッサー機能があります。
簡単にお伝えすると音割れを塞いだり、背景の音と実況の声をバランス調整してくれる機能のことです。
別々に操作をして音量調整をしても良いのですが、オーディオインターフェイスがあれば簡単に解決できます。
こうした理由から、オーディオインターフェースはライブ配信にはぜひオススメの機材であると言えるでしょう。
オーディオインターフェイスのループバック機能とは?

オーディオインターフェイスの機能にはループバックがあります。
この機能は出力チャンネルから出る音を、入力チャンネルへと送る機能のことです。
ループバックを使うことで、パソコン上の音を相手に送れるようになります。
例えばライブ配信をしている時に
といった時にループバックが役立ちます。
このループバック機能ですが、多くのオーディオインターフェイスに搭載されています。

ただし絶対ではありません。
そうした場合は、ケーブルを使って再現することも可能です。
その際にはケーブルの間に、オーディオミキサーをはさむことで応用した使い方もできます。
ただケーブルの場合は無限ループになることもあるので、注意が必要になります。
オーディオインターフェイスの選び方のコツ
オーディオインターフェイスを選ぶには、どんなコツがあるのでしょうか。
いくつか押さえておきたいポイントがありますので、1つずつ確認していきます。
ただその間に使用環境の確認も行っておくといいです。

基本的にオーディオインターフェイスの接続にはUSB端子が使われます。
これにはOSは関係ありません。
MacでもWindowsでもUSB端子が使われているため、基本的にはOSによる違いはないと考えて問題ないでしょう。
ただしプラグインの問題などは残るので、後は機材ごとに確認をしなくてはいけません。
USB端子ですが主にUSB-タイプAとUSB-タイプB、USB-タイプCの3つのタイプがあります。
パソコンで最も多い端子はUSB-Aです。規格としてはUSB2.0とUSB3.0が一般的になっています。
数字の違いで転送速度が異なっていますが、どちらでも接続は可能です。
最近発売されたパソコンや、オーディオインターフェイスだとUSB3.0に対応しているでしょう。
USB-Bはプリンタやスキャナなどで採用されている端子です。
一部のオーディオインターフェイスにも採用されています。
最後のUSB-Cですが、こちらはスマートフォンで採用されているタイプです。
Macで使われているThunderbolt端子との互換性があり、変換ケーブルがあれば接続ができます。
ライブ配信に使う場合はUSB3.0で接続できるオーディオインターフェースがオススメです。
転送速度が速く大量のデータ転送が可能となります。
USB3.0は音声だけではなく、高画質の映像信号までしっかりと転送できるためライブ配信向きです。
ちなみにThunderboltの場合だと、USB-Cへの接続できるのがThunderbolt3になります。
転送速度は最大で40Gbpsとなっています。

サンプリングレートというのは、音質の良さを数値で示したものです。
音声信号を1秒間に記録する回数のことで、kHzで表示されます。
この数値が大きくなるほど音質が良くなります。
もう1つ音質としては量子化ビット数もあります。
こちらは音声信号の振幅を示したもので、数値が高いほどアナログ信号を忠実にデジタル信号に変換していることになります。
| 16bit 44.1kHz | 音楽CDの標準的な情報量 |
|---|---|
| 24bit 96kHz | 16bit 44.1kHzの3倍の情報量 |
| 24bit 192kHz | ハイレゾ音源。音楽CDの約6.5倍の情報量となる |
ハイレゾ音源は人間の可聴領域を超えており、その違いは聞き分けることができないとも言われています。
しかし、音声を収録して編集ソフトでボリュームを上げるといったことを行った場合、サンプリングレートが高い(情報量の多い)音声データの方がノイズが少なくなります。
オーディオインターフェースを選ぶ際はこの2つの数値を見て、できるだけ大きな方を選ぶようにしましょう。

ライブ配信をするためにオーディオインターフェイスを購入するのなら、ループバック機能と内蔵エフェクト機能に注目しておきます。
ループバック機能は、デジタル音源とアナログ音源をミックスして配信するのに必要な機能です。
またパソコン上で流している音楽を、配信にのせることもできるようになります。
この機能があればパソコンで再生したカラオケに、マイクで歌声を乗せることも可能です。
ループバック機能がなくても、パソコン内で同じような処理はできます。
ですが前述したように、遅延や音質の劣化があるのでおすすめできません。
もう1つ内蔵エフェクトとは、オーディオインターフェイスを通して音声や楽器の音に効果をつけることを指します。
例えば男性の声を女性のように加工したり、楽器の演奏に加工することも可能です。ライブ配信における表現の幅を広げるためには、必須の機能だと言えるでしょう。

オーディオインターフェイスには、様々な入力端子があります。
ハイスペックな機種になるほど、端子の種類や数が豊富になるのです。
つまり一度に様々な音や声を同時に入力できると考えてください。
どんなライブ配信を行うのか、これによって必要な入力端子が変わってきます。
高額な機種を購入すれば良いと適当に選んでしまうと、オーバースペックで機能を使い切れないというケースも少なくありません。
そのため入力端子を確認するのは重要です。
トークライブ用オーディオインターフェイスの選び方

次にトークライブ用オーディオインターフェイスの選び方を確認しましょう。
最近のライブ配信需要増もあり、近年ではトーク配信向けに機能が最適化されたオーディオインターフェイスも発売されるようになりました。
先述したループバック機能もその1つになります。
トークライブ配信だと他には効果音がつけられるようなエフェクトがあると便利です。例えばボタンを1つ押すだけで、ラジオのようにきっかけ音を出すこともできます。
また声にエコーをかけたりすることで、トークの表現幅を広げられるでしょう。
トーク中でも1人で簡単に操作できるような、インターフェイスを備えた機種も少なくありません。
こうした機材を選ぶことで自分1人で配信をしながら、手元でライブ配信用の操作を苦もなく行えるのです。

YAMAHA AG03はループバック対応のオーディオインターフェイスです。
音楽と音声用に3チャンネル搭載となっていて、60mmのフェーダーで快適なボリューム操作ができます。
ウェブキャスティングミキサー機能で配信をサポートしてくれる
ヘッドセットマイク端子あり。ファンタム電源も対応
大型のボリュームコントロールが便利
タフでコンパクトな外装のため携帯性も高い
有名な音楽機器メーカーであるヤマハ製であり、ハイレゾ音質でアナログ音源を忠実に再現してくれる品質の高さが売りになります。
ライブ配信用の機能も豊富で、特にヤマハのDSP技術を搭載したエフェクトが便利です。
トークのボリューム調整が直感的に行えるだけではなく、リバーブなどのエフェクトもワンタッチで利用できます。
またバンドルされているアプリを使えば、DSPの設定を変えることも可能です。
USBでの接続になるのですが、iOSデバイスにも対応しています。

前段で紹介したYAMAHA AG03の上位機種になるのがYAMAHA AG06です。
より専門的な機能が充実しているので、音楽のライブ配信をしたい人におすすめのオーディオインターフェイスだと言えるでしょう。
ヘッドセットマイクに標準対応
ダイナミックマイク×2、ファンタム電源搭載
ループバック対応
ワンタッチDSP対応
上位の機種だけあって、充実した機能があります。
マイクプリアンプにも高性能な物が採用されていて、細かいニュアンスまで再現できるので音楽配信に向いています。
またトークライブでも高音質なライブ配信をしたいのならおすすめです。
ワンタッチでエフェクトがかけられるDSPに対応していてループバック機能もあるので、ライブ配信をするのにも向いています。
さらに機能の充実があるため、音楽をしっかりと作成することも可能です。
ちなみにUSBバスパワーにも対応しています。そのためモバイルバッテリーでの駆動もできます。
携帯性に優れているため、屋外で配信をしたい人にも向いている機材です。

安価なオーディオインターフェイスを探しているという人におすすめなのが、ベリンガーのUM2です。
オーディオインターフェイスとしては、かなり安価な部類に入りますので初心者用としても期待できます。
価格が安価である
ASIO非対応なのでWindowsよりもMac向き
マイクと楽器用がそれぞれ1つずつ入力できる
ファンタム電源対応で高品位なマイクプリアンプ搭載
オーディオインターフェイスとしては最低限必要な機能があるのが特徴です。
複雑な機能がないからこそ、シンプルな操作が行えます。
何も知らない初心者の方でも直感的に使えるのが特徴でしょう。
ただしASIO非対応であるため、Windowsで使うのにはあまり向きません。
音楽用に使うのには心もとないのですが、トークライブ中心に使う程度であれば問題ないでしょう。
ただし音質にこだわりたいのなら、Mac専用だと考えた方がいいです。
あくまでもエントリーモデルになるため、とりあえずオーディオインターフェイスを使ってみたいという人に向いた機材です。

スタインバーグのUR22Cは、非常に人気の高いオーディオインターフェイスです。
価格的にはそこまで安価ではありませんが、コストパフォマンスとして考えた場合は最高の機材でしょう。
本体内にミキサーやエフェクト機能を搭載
USB-C対応
高音質なサウンド
iOSデバイスでも対応できる
新しい機材であるためUSB3.0に対応しています。
中低音域が分厚くなるサウンドの良さには定評があるので、音楽用ライブ配信にも十分に使えるでしょう。
価格的には安いとは言えませんが、搭載されている機能は本物です。
そのため価格以上の価値があるオーディオインターフェイスでしょう。
近年の需要増によって、品薄になるくらい人気があります。
DSPも本体に搭載しているため、パソコンに負担をかけずにエフェクト処理が可能です。
プロ仕様のプラグインとは比較が難しいですが、エントリー機でDSP機能が内蔵されているのは高いコスパの証です。

タスカムのUS-2x2HRはマルチメディアクリエイター向けの機材です。
ハイレゾ音源での録音もでき、オーディオ性能が旧機種よりも向上しているのが強みになります。
コンパクトで多機能な機材だと言えるでしょう。
ループバック機能対応
低レイテンシで安定したドライバが使える
新しい製品なので高機能です
シンプルで直感的な操作ができる
2チャンネルのマイクとギター入力に対応可能な端子となっています。
USB-C対応で楽器と音声の同時録音が可能です。
サウンドの作成にも強く、高品質なマイクプリアンプも搭載しています。
またダイレクトモニター方式を採用することで、遅延のないモニタリングが可能です。
ライブ配信用として使えるループバック機能にも対応しています。
手軽にライブ配信ができる構成になっていて、配信ソフトのOBSも利用可能です。
人気製品のリニューアルモデルで、なおかつ完成度が高いオーディオインターフェイスです。
そのため音楽用としてもライブ配信用としても使える懐の深さがあります。
音楽ライブ用オーディオインターフェイスの選び方

次に音楽ライブ用オーディオインターフェイスの選び方を確認します。
音楽ライブと一口にいっても1人で弾き語りをするのか、バンド演奏をするのかで選ぶ機材も違ってくると言えるでしょう。
例えばバンド演奏をライブ配信をする場合は、ステレオマイクを使った方法や、各楽器ごとに音を入力するのかでも違ってきます。
反対に弾き語りライブであれば、最低限の機材ですみます。
例えばオーディオインターフェイスでも多チャンネルではなく、マイク1つと楽器用入力の1つがあれば十分でしょう。
いずれの場合でもオーディオインターフェイスには、ミキシング機能が搭載されている機材がおすすめです。
これは入力した音源が右と左で別れてしまわないために行います。

クラシックプロのMX-EZ4は、オーディオインターフェイスにアナログミキサーの機能を搭載しているのが特徴です。
コンパクトな本体なので、場所を取らないというのもポイントでしょう。
ファンタム電源対応のマイク入力が2系統
シンプルで直感的な操作ができるインターフェイス
価格が比較的に安価である
MX-EZ4は初めて音楽ライブ配信をする人におすすめの機材です。
最低限の機能が最低限の価格で購入できることもあり、高い人気があります。
バンド演奏用としては少し心もとないですが、弾き語り用には十分なスペックがあるでしょう。
コンパクトなボディに直感的な操作ができる設計がなされているので、初心者でも問題なく利用できます。
できることが少ないため、操作そのものもシンプルになるのです。
入門用の機種としては十分な機能があるので、とにかく音楽ライブ配信をしたい人に向いています。
ミキサーとしての機能もあるので、手軽に音楽配信ができる機材としておすすめです。

ベリンガーのUMC204HDは、MIDAS設計のマイクプリアンプを搭載している機種です。
内部の処理はハイレゾ音源に対応していて、著名な音楽制作ソフトとの互換性もあるのが強みだと言えるでしょう。
外部エフェクターを導入できるインサート端子あり
ダイレクトモニターに対応可能
超低レイテンシのドライバが無料でダウンロード可能
USBバスパワー駆動なので携帯性もあり
コンパクトな筐体にHI-Z入力に対応したジャックが搭載されています。
2IN4OUTの入出力ができ、ハイレゾ音源にも対応しているのが特徴です。
MIDASのマイクプリアンプも2機搭載されていて、音質面でもしっかりとサポートしてくれるでしょう。
音楽用のオーディオインターフェイスとしては、十分なパフォーマンスがあります。本体も小さくて携帯性があり、メタル筐体のため堅牢性も高いです。
自宅でのライブ配信以外にも、外部で収録する時にも役立ってくれます。

オーディエントらしくないオーディオインターフェイスがevo4です。
デザインとしてもシンプルで、搭載されている機能も悪くありません。
そのため入門用の機材として高い人気がある機種だと言えるでしょう。
入力ゲインを自動調整してくれるスマートゲインが便利
プラットフォームを選ばない柔軟な接続機能
ループバック機能対応
コンパクトで携帯性に優れた本体サイズ
evo4も入門用のオーディオインターフェイスとしておすすめの機種です。
価格的にも安価な部類に入りますし、何よりも本体がコンパクトで使い勝手が良いのが特徴でしょう。
特筆しておきたいのが、独自機能であるスマートゲインです。
入力された音量を自動で調整してくれるため、音楽制作やライブ配信用としても非常に便利な機能だと言えるでしょう。
シンプルで直感的な操作ができるインターフェイスや、コンパクトながら高い音質など十分な機能も搭載しています。
初めてのオーディオインターフェイスとしても十分でしょう。

ヤマハのMG10XUは価格帯の割には高コストパフォマンスの機材です。
この項で紹介した他の3機種と比較すると、価格の高さは否めません。
ですが搭載されている機能や、ライン入力の豊富さは追随を許さないのが特徴でしょう。
バンド演奏用のオーディオインターフェイスとしても機能十分
ハイクオリティなサウンドを提供するオペアンプを搭載
最大で4マイク10ラインの入力ができる
D-PREのマイクプリアンプ搭載
MG10XUは価格帯の割には多彩な機能を搭載している機種です。
D-PREのマイクプリアンプを搭載したことで、原音を忠実に再現してくれる実力があります。
さらに高品質なオペアンプも搭載ずみなので、音楽の質という点はかなり高いと言えるでしょう。
配信用の機能としてはSPXのデジタルエフェクトを搭載しています。
エディットが可能な24種類のプログラムが用意されているのも強みです。
オプションになりますが、フットスイッチをつければフット操作もできます。
ライブ配信用のオーディオインターフェース9選 まとめ
この他にも優れたオーディオインターフェースがありますので、ココで解説したオーディオインターフェース選びのポイントに注意しながら用途に合った製品を選んでください。
最初はあまり高価な製品を選ばず、必要になったら買換えて使うのをオススメします。
ライブ配信についての相談を下記ページで受け付けています。
オーディオインターフェースやライブ配信機材についてお気軽にご相談ください。